「明治150年」であるためか、日本近代関連書の出版や復刊が相次いでいる。大河ドラマの「西郷(せご)どん」(林真理子原作)関係はもちろん、たとえば中公文庫でも、石光真清の手記が新編集で復刊されたり*1、橋本昌樹の『田原坂』が増補新版で刊行されたり*2している。
この流れに乗って、中村きい子『女と刀』(講談社文庫1976←カッパ・ノベルスジャイアントエディション1966)も復刊してくれないものだろうか、と思う。
語り手の「わたし」=キヲ*3は、西南の役(明治10〈1877〉年)の5年後、鹿児島・黒葛原(つづらばら)で年貢取締りの実権を有した名頭(みょうず)の権領司(ごんりょうじ)家の直左衛門とエイとの間に長女として生れた。薩摩の一外城(とじょう)士族の出ではあるが、里では「有士(きけて)」といわれる立場にあり、城下士族も一目置く存在であったらしい。
直左衛門は、西郷隆盛のもとで西南の役を戦い、「熊本鎮台を踏みしだく意気で、熊本城を攻めた」(p.21、講談社文庫版。以下同)経験をもつ。この「十年のいくさ」で「日本」そのものに敗北したことが、直左衛門の生涯を決定づけており、彼の子育ても、時代に抗して「野(や)にある権領司という郷士の『鋼』の精神をうちこんでおかねばならぬ」(p.27)といった信念のもとで行う劇しいものであった。
ゆえに娘のキヲも、「世間のしきたりに抗って生き」る(p.78)ことを信条としている。それは、「士族という身分によりいっそうの強い誇りをも」ちながら(p.98)*4、一方で「血の体制(まとまり)」なる羈絆を否定し、「おのれの血ひといろに染めあげていくという、そのたたかいにかぎりない執着をもつ」(p.248)といった強烈な自家撞著でもある。誤解をおそれずに云えば、主人公は、近世以来の国家体制と近代的自我の自律性との間で引き裂かれているように見える。しかしキヲが、作品冒頭で「名頭の役」「名頭という役目」をしきりに強調していることから、これがそもそも古来の強制性を伴う「役」ではなく、個人の存在意義を支える「役」であったことが知られるのであって、そうだとすれば、「士族という身分」「おのれの血ひといろ」は、キヲの精神に容易に同居しうるものだったといえる。
尾藤正英氏によると、日本近世の「役」は、「自発的に、その責任を果たすことに誇りを感じて、遂行されるような義務」、「それぞれの身分に所属していることの象徴的表現とでもいうべき性格が強く(略)個人の自発性に支えられたもの」であり(「序説 日本史の時代区分」『江戸時代とはなにか―日本史上の近世と近代』岩波現代文庫2006:22-23*5)、その点から、強制性を有する古来の「役」とは区別されるという。そしてこれを、日本独特の「『役(やく)』の観念」と位置づけている。キヲは生涯、古来の「役」を引きずった「日本」そのものと対峙し、それに反撥し続けたとも解釈できるのではないか。
この作品で特に「読みどころ」となるのは、太平洋戦争末期、キヲが自らの末娘の名古屋行きを阻止せんと、その末娘・成に刀をつきつける場面(pp.280-83)であろうが、そこでキヲが持ち出すのが、「十年のいくさ」というイエにとっての「痛苦の歴史」である。そして、「日本」とアメリカとの戦争を「わたしのいくさではないこのいくさ」(p.282)と突き放してみせる。しかるに、戦後に至ってもキヲは、父親がかつて「文明開化」を軽蔑したのと同じように、「民主主義なるもの」を否定し去るのだ(pp.292-93)。
いわゆる“名文”ではないし、独特の方言も頻出するし*6、「種子田(たねだ)という人のもとに私淑した」(p.169)といった表現があったりもするが、とにかく形容しがたい迫力に満ちた小説なのである。
講談社文庫版の解説(鶴見俊輔)は、次のように評している。
この本には、明治以後の百年を、この本一冊によって見かえすほどの力がある。明治百年が日本の男が表にたって指導した歴史であったことと考えあわせるならば、明治以後の日本の男たち全体を見かえす力がある。その明治百年が、敗戦後の年月をふくめていることは勿論のことで、この本は、戦後民主主義批判の書でもある。戦後日本の民主主義を批判するだけでなく、地上のさまざまの民主主義のそだてやすい人間性のもろさを見すえてしかりつけるようなきびしさをそなえている。
そのしかりつける語り口は、男にだけむけられるものではない。女もまたしかりつけるだけの公平さをもっている。こうしかりつけられていてはかなわないという感想も、時にはわいてくるのだけれども、男はみなよくない、女は正しいというような思想によって書かれた本ではなく、人間全体をしかりつけるすがすがしい語り口に感動する。(p.335)*7
「明治以後の百年を、この本一冊によって見かえすほどの力がある」など、いささか評価が高すぎるようにも思うが、鶴見氏はこの作品にかなり感銘を受けたらしい。たとえば加藤典洋氏は、鶴見俊輔『文章心得帖』(ちくま学芸文庫2013)の文庫版解説「火の用心―文章の心得について」*8で、次のように述べている。
私は一九八〇年代半ばから九五年の休刊にいたるあいだ、『思想の科学』の編集委員として鶴見さんとおつきあいさせていただいた。その間、書き手として個人的に、鶴見さんにこれを読め、そしてこれについて書け、といわれた本が二冊ある。一つは中村きい子の『女と刀』、もう一つは、仁木靖武の『戦塵』である。ともにそれほど名高いものではない。特に後者は私家版の戦記。なぜということはいわれなかったし、聞かなかった。この二つの本は、読んで書くのが大変だった。ごろごろと石だらけの土地を開墾し、耕作地に変えて、それから種を播き、収穫するような難儀さがあった。(pp.215-16)
『女と刀』は、1967年にTBS系の「木下惠介アワー」枠でドラマ化された(中原ひとみ主演)。その脚色に携わったのが山田太一氏で、山田氏の『月日の残像』(新潮文庫2016←新潮社2013)には、まさに「『女と刀』」という一文*9が収めてある。
山田氏も、前述のキヲと末娘とが対峙する場面を紹介している。
父の無念は、「意向」を「こころ」といい替えられて、主人公に伝えられて行く。第二次大戦の敗色が濃くなるころになっても、これは大久保(利通―引用者)たちのつくった「日本」の不始末で、かかわりなどあるものか、と軍需工場へ行って国のために戦うという娘に、主人公は刀をつきつけて行かせぬといって押し通す。周囲から非国民呼ばわりされても「なんとよばれようがわたしゃ覚悟のうえでやったことじゃよ」と動じない。(p.157)
さて山田氏の「『女と刀』」は、彼がかつて書いた随筆のことから書き起こされている。
ほぼ三十年前の、短い私の随筆が、ある新聞のコラムで、要約という形で言及された。その内容に「何故そんなことをいうのか」という数通の反応があった。おかげで忘れかけていた自分の文章を読むことになった。
私なりに要約すると、湘南電車の四人掛けの席で、中年の男が他の三人(老人と若い女性と私)に、いろいろ話しかけて来たのである。(略)
ところがやがて、バナナをカバンからとり出し、お食べなさいよ、と一本ずつさし出したのである。私は断った。「遠慮じゃない。欲しくないから」「まあ、ここへ置くから」と男はかまわず窓際へ一本バナナを置いた。
食べている老人に「おいしいでしょう」という。娘さんにもいう。「ええ」「ほら、おいしいんだから、お食べなさいって」と妙にしつこいのだ。「どうして食べないのかなあ」
そのうち食べ終えた老人までが置いたままのバナナを気にして「いただきなさいよ。せっかくなごやかに話していたのに、あんたいけないよ」といい出す。
そのコラムの要約は「貰って食べた人を非難する気はないが、たちまち『なごやかになれる』人々がなんだか怖いのである」という私の文章の引用でまとめられている。(pp.153-54)
そして、これを受けるかたちで、
私はかつて「なごやかになれない人」の結晶のような人物を描いた小説をテレビドラマに脚色したことがある。脚本家になって一年目のことだった。鹿児島の作家・中村きい子さんの「女と刀」である。企画は木下恵介さん、はじめの三回は木下さんが書き、あとを引き継いで三十分二十六回のドラマだった。(p.155)
と書き、「もしこれが映画だったら、木下恵介監督の代表作の一つになったかもしれないと、ひそかに思っている」(p.159)と記しているのである。
ちなみに、山田氏の「短い私の随筆」というのは「車中のバナナ」で、一昨年の三月に出た『昭和を生きて来た―山田太一エッセイ・コレクション』(河出文庫)に収められ、さらに昨秋には、頭木弘樹編『絶望図書館―立ち直れそうもないとき、心に寄り添ってくれる12の物語』(ちくま文庫)にも収められた。編者の頭木氏は、作品解説を兼ねたあとがきで、「私は、このたった三ページの作品が、好きでたまりません。/なぜといって、『これこそ、私が人間関係で苦しんできたことだ!』という典型的な状況が、見事に表現されているからです」(p.350)と評し、『月日の残像』にその後日譚が書かれていることに言及している。
わたしがこの『月日の残像』に触発されて再読したのが、フェルナンド・ペソア/澤田直訳『[新編]不穏の書、断章』(平凡社ライブラリー2013)なのだが、それについては、また稿(項?)を改めて述べることにしたい。
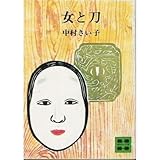
- 作者: 中村きい子
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1976
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 尾藤正英
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2006/04/14
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

- 作者: 鶴見俊輔
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2013/11/06
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 山田太一
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2016/05/28
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (5件) を見る

絶望図書館: 立ち直れそうもないとき、心に寄り添ってくれる12の物語 (ちくま文庫)
- 作者: 頭木弘樹
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2017/11/09
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (5件) を見る