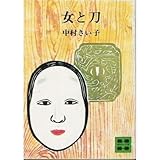池永陽一『学術の森の巨人たち―私の編集日記』(熊本日日新聞社2015)は、講談社学術文庫の編集者(出版部長)だった池永氏の回想録であるが、そこに由良君美『言語文化のフロンティア』(講談社学術文庫1986)を編んだ切っ掛けについて語ったくだりがみえる。
この『言語文化のフロンティア』は、言語や日本語について私がこれまでに抱いていた概念や知識を根本から問い直すきっかけを与えてくれた忘れられない本である。
じつは、国文学の別冊特集号『知についての100冊』に目を通していた時、その一冊として紹介されていたのが由良君美先生の『言語文化のフロンティア』であった。魅力的な異色のタイトルに引かれ、早速どんな本だろうかと、創元社刊の原本を手に入れ読んでみた。そこには私が今まで知らなかった言葉や言語文化についての興味深い論考がいくつも収められていた。(略)
本書の中でも私が特に啓発されたのは、第2章の日本語の再発見に収められた「〈ルビ〉の美学」である。ルビ(ふり仮名)については、これまであまり関心もなく、単に漢字の読みを助けるための補助的なものと思っていたのだが、どうしてどうして、ルビは文章を、日本語を左右するほどの大きな働きをしていることを初めて教えられたのだ。(pp.97-98)
これに触発され、久々に「《ルビ》の美学」を再読するため学術文庫版の『言語文化のフロンティア』を手に取って、冒頭からじっくり読み直していたところ、次のような記述があることに気が付いた。
方言は、言うならば、地域コンミュニティーという個がもつ言語的多義性の一種と言ってよいだろう。おなじ地域コンミュニティーのなかの、おなじ階層に属していても、個々人の言語学的特徴の差異には驚くべきものがある。
ちょうど顔のようなものだ、といったらよいだろうか。アメリカ人には日本人・韓国人・中国人の区別はできにくいらしいが、われわれ同士にはできる。イーヴリン・ウォーのある小説に、主人公のイギリス青年がアメリカに来て、アメリカ娘が誰も彼も、まるで規格品のように、おなじ姿態と顔付きをしているのに困り、「中国人の母親は、自分の娘たちを――西欧人には皆おなじにみえるのに――ちゃんと見分けるという話だが、アメリカの母親も見分けられるんだろうな」と考え込んでしまうシーンがあった。冗談ではない。自分の子供たちはおろか、手広く国内を歩いている人なら、顔とおなじだ、方言の微妙な差異は、頭のなかに地図のように描きあげられているにちがいない。(pp.15-16)
この「イーヴリン・ウォーのある小説」というのは、たぶん“The Loved One”だよな、と微かな記憶を頼りに、イーヴリン・ウォー/小林章夫訳『ご遺体』(光文社古典新訳文庫2013、以下「小林訳」)を索ってみると、やはりそうで*1、
彼女が部屋を出て行くと、デニスはすぐにこの女性のことをすべて忘れてしまった。どこにでもいるタイプだった。アメリカの母親は、離れていても娘の見分けがつくのだろうとデニスは考えた。中国人は見かけは同じように見える人種だが、微妙な違いでお互いを区別できるという。それと同じだ。(p.70)
とあった。由良の文章には「中国人の母親は」云々とあり、若干ニュアンスが異なるのだが、そもそもこの小説自体、『ハムレット』(p.69)、A.E.ハウスマンの詩(p.135)、アーネスト・ダウソンの『詩集』序文(p.181)等から、故意に不正確な引用をしている節がある。だからといって、由良も意図的にそうしたのかも知れない……などと考えるのは、おそらく穿ちすぎなのだろう。
さて小林訳が出たのと同年同月(!)に、“The Loved One”のもう一つの邦訳書として、イーヴリン・ウォー/中村健二・出淵博訳『愛されたもの』(岩波文庫2013、以下「中村・出淵訳」)というのが出ている。これは、1969年に金星堂から出た旧訳に中村氏が手を加えたものらしい。
ちなみにその訳書では、当該箇所が、
彼女は部屋を出て行き、デニスはじきに彼女のことをすっかり忘れてしまった。彼は今までに彼女と至る所で会っていた。ちょうど中国人たちがどれも見た目にはひとしなみの姿かたちをしていながら、お互い同士、微妙な区別がつくと言われているように、アメリカの母親たちは自分の娘たちを別々に見ても見分けがつくのだろうと、デニスは思った。(p.71)
となっている。
“The Loved One”という原題は、たぶん、ラスト直前のデニスの次の言葉――「要するにわれわれがやらなければならないのは、“ご遺体”を、こう言わせてもらうが、ここへ連れてくることだ」(小林訳p.201)、「今僕たちがしなければならないのは僕たちの『愛するもの』――こんな呼び方をしていいならの話だが――を収容して、ここに持って来ることだ」(中村・出淵訳p.204)という箇所に由来するものだろうが、この「ご遺体」「愛するもの」が具体的に何を指すのか明かしてしまうと、いささか興をそぐことにもなりかねないので、ここでは触れずにおく。
また作中、デニスが観光案内映画の音声に耳を傾ける場面で、小林訳は「(神に)愛されし人」に「ラブド・ワン」とルビを振っているところがある(p.99)*2。これこそまさに、由良の「《ルビ》の美学」いうところの、「日本語の〈黙読二国語性〉を修辞力の増強に転用」(p121)した例のひとつといえよう。由良は当該文で、黄表紙本や洒落本におけるルビを例にとって、そこに「まず漢訳し、つぎに邦訳する一種の〈ひとり重訳〉とでもいうべき二重手続き」(同)という手法を見出しているのだが、「愛されし人(ラブド・ワン)」の例は、文語訳した表現に原音に基づくカナ表記を施すという「二重手続き」を行っているのであり、いわゆる現代「口語文」内におけるルビの振り方としては、もっとも「超前衛的」(こちらも由良の表現)だと言いうるだろう。
ところで“The Loved One”には、他にも邦訳があるらしく、吉田誠一訳(早川書房1970)は『囁きの霊園』というタイトルで*3、また出口保夫訳(主婦の友社1978)は『華麗なる死者』というタイトルで出ていて、同一作品なのにバラバラでややこしい。しかしそこは、この作品が暗喩に満ちており、多様な解釈を許すため結果的にそうなったのだとも受け取れる。
“The Loved One”は映画化もされている。邦題は『ラブド・ワン』であり、これはわかりやすい。しかし高崎俊夫氏によると、ウォーの“Decline and Fall”(小説名としての邦題は『衰亡記』『大転落』など)が1970年代半ばに、『おとぼけハレハレ学園』という「実にふざけた題名」となって深夜のテレビ映画で放送されたことがある(劇場未公開)のだそうだ(「イーヴリン・ウォー原作の幻の未公開映画」*4『祝祭の日々―私の映画アトランダム』国書刊行会2018)。高崎氏はこの作品を「抱腹絶倒の傑作」と評したうえで、
とにかく、めまぐるしいばかりのテンポのよい語り口、主人公以外、全員気が狂っているような、『不思議の国のアリス』を思わせるナンセンスで馬鹿馬鹿しいギャグが次々に飛び出し、ラスト、悪夢のような遍歴を経て、平原の彼方へ走り去ってゆく主人公に、思わず、『幕末太陽傳』(57)の居残り佐平次を連想したものである。(p.11)
と述べている*5。

- 作者: 池永陽一
- 出版社/メーカー: 熊本日日新聞社
- 発売日: 2015/08/13
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 由良君美
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1986/05
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 5回
- この商品を含むブログ (12件) を見る

- 作者: イーヴリンウォー,Evelyn Waugh,小林章夫
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2013/03/12
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: イーヴリン・ウォー,中村健二,出淵博
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2013/03/16
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (9件) を見る

- 作者: 高崎俊夫
- 出版社/メーカー: 国書刊行会
- 発売日: 2018/02/27
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
*1:そもそもウォーの作品自体、そんなにたくさん読んだことがないので、当然といえば当然の話なのだが。
*2:中村・出淵訳は単に「死者」と訳している(p.100)。
*3:これは作中に登場する霊園の名称をそのままタイトルに用いたものだが、中村・出淵訳は「囁きの森」と訳している。
*4:この文章は2011年8月にネット上で発表されたものだが、本では補注の形で『愛されたもの』『ご遺体』が刊行されたことがフォローされている(p.13)。
*5:同書は、世にあまり知られていない映画や文章を多く紹介していて、とりわけわたしは、エリザベス・ボウエン『日ざかり』を原作とする英国映画が『デス・ヒート/スパイを愛した女』という邦題でVHS化されていることや、秦早穗子氏が映画誌に厖大な量のエッセイを書いていることなどが気になった。他にも刺戟されたところや記憶が喚起された記述が多々あったのだが、それらについて書くのはまたの機会にしたい。
![泥棒成金 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD] 泥棒成金 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51uRSIOt02L._SL160_.jpg)

![弁天小僧 [DVD] 弁天小僧 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/6135b%2BSV1oL._SL160_.jpg)
![アンタッチャブル(通常版) [DVD] アンタッチャブル(通常版) [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/511-I%2B9q%2B9L._SL160_.jpg)
![殺しのドレス (2枚組特別編) [DVD] 殺しのドレス (2枚組特別編) [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51nXEcwn5UL._SL160_.jpg)


![新婚道中記 [DVD] 新婚道中記 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZTa0sxk-L._SL160_.jpg)