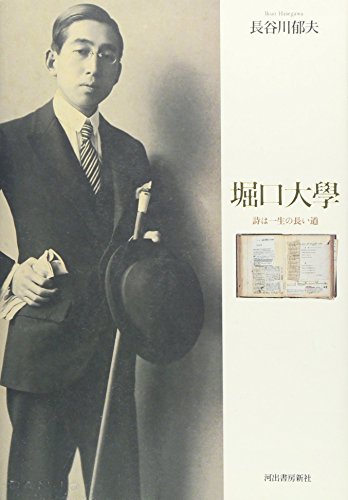いまも新刊で買えるのかどうか分らないが、田中慶太郎編譯『支那文を讀む爲の漢字典』(研文出版1962,以下『漢字典』)という辞書がある。これはもともと1940年に田中慶太郎の文求堂から刊行されたもので、1962年の四版から版元が「(山本書店出版部)研文出版」に変っている。その際には長澤規矩也の「重印の序」も附された。手許にあるのは1994年の十版で、高校生の時分に新刊書店で購ったのだった。
この書物の実質的な翻訳者が松枝茂夫であるということについては、かつて安藤彦太郎が、次のように書いていた。
中国の古典を中国のものとして読むための手ごろな字典の刊行を企画した田中慶太郎という人物は、具眼の士といえるであろう。田中氏については、『急就篇』の発売元である文求堂の主人として、すでに紹介した。竹内好さんも「田中慶太郎氏のこと」という文章(『中国を知るために』第一集、一九六七年)を書いて、その識見を称揚している。その字典というのは、文求堂発行の『支那文を読む為の漢字典』(一九四〇年。戦後、山本書店・書籍文物流通会から再刊)である。
この字典の原本は、陸爾奎・方毅共編『学生字典』(一九一五年、上海商務印書館)という小字典で、田中慶太郎編訳となっているが、松枝茂夫さんが実際の翻訳にあたり、さらに『辞源』などを参考にして増補したものである。(安藤彦太郎『中国語と近代日本』岩波新書1988:186)
また百目鬼恭三郎も、次の如く書いている。
この辞書は、戦前中国から出ていた『学生字典』を増補和訳したもので、実際に翻訳に当たったのは『紅楼夢』などの訳者として知られる松枝茂夫氏である。収録語数は八千にすぎず、熟語も、語義の中に少し引いてあるだけだが、ひくごとにこちらが知りたがっている語義がつごうよく載っているのは不思議なくらいである。こういう語義の選択は、結局、編纂者の勘に帰すわけで、辞書作りの天才か凡才かは、ここできまるのだろう。語義の説明もまた簡潔にその意を伝えている。たとえば、「言の項の説明は「口が声を発し以て意思を表示する所の者なり。自ら言ふを言といひ、答述するを語といふ」となっている。意を尽くして間然するところがない。
この辞書の存在を教えてくれたのは、いま山口大学にいる東洋史学者の沢谷昭次氏だったろうか。これが、辞書というもののありかたを考えさせるきっかけになったことを、いまでも感謝している。(百目鬼恭三郎『乱読すれば良書に当たる』新潮社1985:80)
この簡便な辞書がかつて重宝がられたのはほかにも理由があって、そのことに関しては頼惟勤氏が、「(『説文解字』の)所属の部首のわかりにくい字や、古今字(古今で字形が相違する字)や、重文などを引くのには困ることがあります。(略)そういう時、文求堂の『支那文を讀む爲の漢字典』が役に立ったものです。しかし、以上は皆、過去の話で、いまは便利な索引がいろいろな形で出ている」(頼惟勤=監修/説文会編『説文入門』大修館書店1983:51)と述べているとおりだ。この件について、『漢字典』はその「例言」で、「説文部首の順位を文求堂で加へた」「かゝる普通字典に説文部首の順位を注したのは本書を以て恐らく嚆矢としよう」などと書いており、それが原書の『学生字典』にはない特色である旨を強調している。
ただしその特色にも難点があって、たとえば「魔」字を引いてみると、「説三四六」とある。「説三四六」というのは、許慎『説文解字』(以下『説文』)の「鬼部」にあることを示しているのだが、これだけを見ると、おそらくは『説文』本文に「魔」字が出現するのかと早合点してしまうことだろう。だが、『説文解字 附檢字』(中華書局1963*1)をみてみると、「魔」字は「魑」「魘」両字とともに、「鬼部」末尾の「新附」というところに掲げてある。この「新附」とは何かというと、北宋の徐鉉(917-91)があとから独自につけたした部分で、実はオリジナルの『説文』にはなかった箇所なのである*2。もっとも、西暦100年頃に成立したとされる『説文』は原本が残っておらず、徐鉉によるいわゆる「大徐本」が長らく標準的なテクストとして扱われてきたから、已むをえないことといえばそれまでの話なのかも知れないが、この記述のみをもって、『説文』が編まれた時代に「魔」字が存在したと速断してしまうとまずいのである。
いきなり話が飛ぶようだが、ここで洪自誠/中村璋八・石川力山=訳注『菜根譚 全訳注』(講談社学術文庫1986)の「降魔者、先降自心」(38)の「魔」字につく注をみてみると、「梵語māraの音写語である魔羅の略。古くは摩羅とも音写され、梁の武帝が「魔」の字を作らせたとも伝えられる」云々(p.70)とある。少し古い辞書――たとえば宇野哲人編『明解漢和辭典 増訂版』(三省堂1927*3)の「魔」字の項にも「梵語の音譯」とあるし、現行の戸川芳郎監修『全訳 漢辞海 第四版』(三省堂2017)にも「梵語(ボンゴ)māraの音訳「魔羅」の略」とある。またたとえば、白川静『字通』(平凡社)も「梵語māra、すなわち悪鬼・外道の音訳語として作られた。唐以後の文献にみえる」と書いている。「梁の武帝」云々は後にも触れるようにあくまで伝説にすぎないとしても、「魔」字が、仏典を漢訳する過程においてサンスクリットの音訳字として生れた漢字であることはまず間違いないだろう。なお、「魔」が梵語由来であるという事実は、昔から日本でもそれなりに知られていたらしく、たとえば道元『正法眼蔵』は「発菩提心」で、『大智度論』の「魔是天竺語、秦言能奪命者」(魔ハ是レ天竺ノ語、秦ニハ能奪命者ト言フ)というくだりを引いている(全訳注 増谷文雄『正法眼蔵(六)』講談社学術文庫2005:324)。
「魔」字の成立事情や伝承についてくわしく述べたものに、船山徹『仏典はどう漢訳されたのか―スートラが経典になるとき』(岩波書店2013)がある。同書は、「梵」「塔」「僧」「薩」「鉢」「伽」「袈裟」などに加えて「『魔』が仏典の漢訳を通じて創成された新字なのはまちがいない」(p.185)と述べたうえで、武帝以前のものと確認できる複数の写本に「魔」字がすでに出現していることを指摘している。さらに武帝を「魔」字の創案者と看做す最初期の資料として、湛然(711~782)『止観輔行伝弘決(しかんぶぎょうでんぐけつ)』(智顗『摩訶止観』の注釈書)を紹介し、かかる説が流布した結果、『康煕字典』にまで採用されたことに言及している。
ところで上に、『菜根譚 全訳注』から「古くは摩羅とも音写され」というくだりを引いたが、船山徹『仏教漢語 語義解釈―漢字で深める仏教理解』(臨川書店2022)によれば、「より古い表記として「摩羅など」を挙げるのは或いは不適切かも知れない。(略)中国には「魔」は「磨」から派生したとする説があるから,元の表記は「磨羅」だったとすべきか」(p.104)という。
ちなみに「魔羅」について補足しておくと、「もともとは「魔界の王」の意で、転じて「修行を妨げる魔物・悪魔」を広くいうようになり、よく知られるように、僧侶の間で「男根、陰茎」を指す隠語として用いられるようになった」(田中章夫『日本語スケッチ帳』岩波新書2014:47)。楳垣実編『隠語辞典』東京堂出版1956)で「まら〔魔羅〕」を引くと、「男陰。〔←仏教で「障害」を意味する梵語からという〕(僧→俗)(鎌)」とあり、鎌倉期には使われていた隠語だとする。また佐藤紅霞『世界艶語辭典』(中村書店1946)というのを引くと、「マラ(麻羅)男陰。まうらとも訛す。元僧侶間の隱語なり。之れ梵語にて麻羅と言ふは修道の障礙擾亂の義なればなり」とあるが、「麻」は誤記であろう。